 悩んでいる人
悩んでいる人
こんな方にオススメの記事です。
この記事のもくじ
はじめに
こんにちは、Hikaruです。
以前の記事で、私はバルブオイルに関して以下のようなことを書きました。
・バルブオイルは販売しているそれぞれの会社が、ピストンの動作だけでなく音響的な面も考慮して開発をしています。
意外と意識しないかもしれませんが、バルブオイルはメーカーによって音色や吹奏感がはっきり変わります。
ですがバルブオイルによってどのような音色や吹奏感の違いがあるのかを知っている方は多くはないと個人的に思っております。私自身も多くのバルブオイルを試した結果、各バルブオイルの違いや特性を知り、自分の好みを知ることが出来ました。
しかしその答えに至るにはお金も時間もかかりますし、音を聞き分けるための耳を鍛えることも必要になります。
そこで今回の記事ではバルブオイルの音色や吹奏感の違いを皆さんに紹介し、バルブオイル選びの参考にしてもらえるよう、実際に演奏した動画も載せていきます。
楽器やマウスピースである程度自分好みの音色に近付くことができたけれども、あと一歩足りないという方は、バルブオイルを変えてみると自分の理想に更に近付くことができると思います。
また演奏会でどのような音が欲しいかによって、バルブオイルを使い分けることもできるようになるでしょう。
ちなみに今回はタイトルの通り「超個人的」かつ「35種類」のバルブオイルを比較した上での感想・レビューになりますので、非常に主観的で長い記事となっておりますので、ご承知おきください。
石油由来と化学由来のオイルの違い(豆知識)
ざっくりですが、石油由来と化学由来のオイルのメリットとデメリットについて先に解説しておきます。
ここから先の各オイルの解説をより深く知るのに役立ちますので、ぜひ一度目を通してみてください。
・メリット:パチパチとはまるようなピストンワークで、高速のアドリブソロなどに向く。
・デメリット:蒸発しやすく、気温が高いと一日に数度注油が必要になるケースもある。
・メリット:蒸発しにくいため、一度の注油で長時間の演奏が可能。防サビ成分を含んでいるので、楽器の寿命を延ばせる。
・デメリット:石油系に比べると、防サビ成分の量によってはピストンワークが重くなる場合がある。防サビ成分の影響で、ゴミが内部に溜まりやすい。
各バルブオイルの紹介
使用楽器:YTR-9335CH
主管グリス:トロンバ
マウスピース:パーク ハグストロムモデル
条件:各オイルの使用前に古いオイルを落とし、ピストン・ケーシング・各抜き差し管を洗浄。
- PDQ
- ヤマハ(スーパーライト)
- ヤマハ(ライト)
- ヤマハ(レギュラー)
- ヤマハ(ビンテージ)
- ヘットマン(ライトピストン)
- ヘットマン(ピストン)
- ヘットマン(クラシックピストン)
- トロンバT2
- ブルージュース
- アルキャス・ファストオイル
- バック
- バック・リンズオイル
- トロンバ・ファストオイル
- デニスウィック
- ホルトン
- BSCハイスピードバルブオイル
- ウルトラピュア
- ウルトラピュア(ウルトラライト)
- ウルトラピュア(ブラックラベル)
- ノマド
- アリシン
- アイルリッヒ
- FATCAT(高粘度)
- FATCAT(通常)
- JMルブリカント(ライト、No1)
- JMルブリカント(ミディアム、No2)
- JMルブリカント(ヘビー、No3)
- アライアンス
- シルキーウルトラライト
- Monster Original
- Monster faster
- Monster smoother
- Monster Doc’s Juice
- Monster Slide Oil(バルブオイルはPDQを使用)
1. PDQ
マウスピースやアンブシュア矯正器具なども出しているワーバートン社製、PDQオイルです。
石油由来のバルブオイルで、エリック・ミヤシロ氏を始め多くのプレイヤーが愛用しています。
粘度は軽めで、石油から製造されているため不純物が少なく、ピストンの動きはかなりスムーズ。パチパチとした軽快なピストンワークが実現できます。
楽器の持つ音色を引き出してくれる、といった感じの使用感で、音色は輝かしいと表現出来ます。明るい音色が好きな方にはストライクなオイルです。抵抗感も少なめで、オープンな吹奏感になるためポップスやジャズなどで使用者が多い印象です。
欠点として石油成分が強いために揮発しやすく、夏場は追加の注油が必要な場合があります。また臭いに独特の油臭さがあるので、苦手な方は注意が必要です。
2. ヤマハ(スーパーライト)
言わずと知れた我らがヤマハ、その中でも最も粘度が軽くされているバルブオイルです。
ヤマハ製のバルブオイルは全てが化学合成により製作されており、PDQの石油系とは全く異なるタッチレスポンスです。
化学系のオイルは基本的に石油系ほどのスピード感は実現できませんが、このスーパーライトは防サビ成分を極限まで減らしているため、オイルの持続性と軽快なピストンワークの両方を兼ね備えています持続性のある石油由来オイル、と言ったイメージです。
ただし防サビ成分が少ないため、注油して長期間放置したままにしてしまうとピストンが錆びてしまう可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
非常にオープンな音色と息を入れれば音が出るほどの軽い吹奏感で、ドバーッとベルから前方へ一直線に音が飛んでいく印象があります。ギラッと突き抜けるような音が欲しいプレイヤーの方は、スタイルによってPDQとヤマハスーパーライトを選んでみると良いでしょう。
3. ヤマハ(ライト)
スーパーライトよりも一段階粘度が高くなったバルブオイルです。
とは言えまだまだ粘度が低いサラサラタイプのオイルなので、新しい楽器に使用することが望ましいでしょう。
スーパーライト同様オープンな吹奏感ですが、音にまとまりが出てきて輪郭もはっきりしてきますので、吹奏楽などの大編成であってもしっかりと存在感を示すことができるように感じました。
音色はスーパーライトほどではありませんが明るめで、抵抗感も少ないので息抜けがとても良いオイルです。
4. ヤマハ(レギュラー)
ライトよりも更に一段階粘度が高くなったオイルで、ヤマハの中でも最もポピュラーなものになります。楽器を購入した時の付属品としてもよく見かけるオイルです。
粘度は中くらいからやや軽めに相当するオイルで、新品から中古、どの楽器にも万能に使っていけるタイプです。音色は明るすぎず暗すぎず、ニュートラルなやや落ち着いた感じになります。
この辺りまで来るとスーパーライトとの違いが明確になり(個人的にはそう感じます)、ライトまでにはなかった音の厚みが出てくるようになります。
抵抗感がしっかりと感じられるようになるので、大音量であってもしっかりと楽器が受け止めてくれるようになります。
ライトまでは霧状に近かった音が、固体のような形を伴って飛んでいくような印象です。抵抗感も丁度良いので、初心者の方であっても使いやすいオイルだと感じました。
5. ヤマハ(ビンテージ)
ヤマハのバルブオイルとしては最後のご紹介になります。最も高い粘度を持つビンテージオイルです。
ピストンとケーシングの隙間(クリアランス)が広がった古い楽器向けのオイルになります。もちろん比較的新しい楽器にも使用可能です。
粘度が高いオイルの音色は総じて密度があり、抵抗感が強くなるので圧力がかかったような音になります。このヤマハビンテージもその例に漏れません。
壁が迫ってくるような音、と表現できる立体感のある音が重たい楽器やこのオイルのような粘度が高いオイルの特徴で、クラシックやオーケストラで打ち込まれるような音を目指す方には良いヒントになるのではないでしょうか。
ただし新品の楽器に使用すると、粘度が高すぎるためピストンワークが悪くなる可能性があります。その場合はオイルを中くらいの粘度にしておいて、マウスピースや別の手段で補うのが良いでしょう。
6. ヘットマン(ライトピストン)
ここからはヘットマンの各種オイルの紹介となります。
ヘットマンのオイルはピストンワークと楽器の保護を両立させるべく、防サビ効果はもちろん、石油系オイルにありがちなゴムなどのパーツ劣化を防ぐことを目指して開発されました。
最初に紹介するのはライトピストンタイプです。名前の通り、ヤマハでいうスーパーライトやライトに相当するオイルです。
ヘットマンでは最も粘度が軽いタイプなのでピストンワークが軽く、高速パッセージの演奏には非常に扱いやすいです。
ヤマハのスーパーライトやライトタイプと音の飛び方が異なり、前者が一直線に突き進むタイプだとしたら、ヘットマンのライトピストンは前方広範囲にスプリンクラーのように放出されていくたタイプの音の飛び方です。
ヘットマンは全体的にヤマハよりも響きが多い音色になる傾向があり、より歌い込むような曲を演奏したい場合にはヤマハよりもヘットマンの方が有用になるかと思います。
7. ヘットマン(ピストン)
3種類あるヘットマンのバルブオイルのうち、真ん中の粘度のタイプになります。
粘度はヤマハのレギュラーよりやや高い程度で、新品から中古、どの楽器にも万能に使っていけるタイプです。
抵抗感がライトピストンに比べてはっきりと感じられるため、音にしっかりとした息圧をかけることで厚みのあるクラシカルな音色を実現できます。
抵抗感があっても吹きにくさを感じさせない辺り、ヘットマンオイルの完成度の高さが窺えます。個人的には今回吹き比べていて、プロムナードを演奏するのに一番合う音色を持つオイルだと感じました。
8. ヘットマン(クラシックピストン)
ヘットマンの中で最も粘度が高いクラシックピストンで、古い楽器や大きめの金管楽器向けのオイルです。
ヤマハビンテージに似た音色ですが、ヘットマンの方が響きが多く、ヤマハの方は密度が濃い音といった印象の違いがあります。
厚みのある暖かい音色のため、イエローブラスの楽器であってもゴールドブラスに近い音色で演奏することができるなと感じました。
抵抗感はこちらの方がヤマハビンテージに比べて僅かに軽いので、厚い音かつ息抜けを重視する方はヘットマンの方が有用となるでしょう。
9. トロンバT2
スライドグリスも販売しているトロンバ社のバルブオイル、T2(ティーツー)です。
多くの学生の方が使った経験があるオイルなのではないでしょうか、なんとなく吹奏楽部の普及率が高いイメージです。高校生の頃に私も使っていました。
比較的粘度が高めなオイルなので、ある程度年数が経った楽器に使用するのが最もオススメです。学校の楽器に使用されている(ような気がしている)のはこれが要因かもしれません。
しっかりとした抵抗感があり、息を多く使うローノートの際にしっかりと楽器が息を受け止めてくれるようになります。張りと芯のある音で演奏したい方、特に中編成から大編成の吹奏楽などで真価を発揮するオイルです。
ややゴミが溜まりやすいので、時々ボトムキャップを外して掃除してあげると良いでしょう。特徴的な臭いがあるので、苦手な方はご注意を。
10. ブルージュース
青いオイルが特徴のブルージュースです。PDQと並んで世界中のプレイヤーに愛されています。
石油由来のオイルかつ粘度が低いためピストンワークが大変良く、揮発を防ぐように成分が調整されているため、一度注油するとかなり長持ちします。その点ではPDQより優れています。
雑菌の繁殖を防ぐための処理と防サビ処理がされているため、楽器へのダメージがとても少ないオイルです。楽器を清潔に保ちたい方には特にオススメです。
雑味のない素直な音色と軽やかな吹奏感を持つためジャンルを問わず使用することが可能です。ジャズやスタジオミュージシャンであれば歯切れの良い音と少ない抵抗感による息抜けの良さを体感できます。
細やかなフレーズを軽やかに演奏できるポテンシャルを持つオイルのため、クラシックプレイヤーであっても問題なく使用できます。
防サビ効果を持つためビンテージの楽器に使用されることもあり、どの状態の楽器であっても使用できる汎用性の高さを持つオイルで、これからも長く使われていくでしょう。
11. アルキャス ファストオイル
一時期販売終了が噂されてひと騒ぎが起きたアルキャスのバルブオイルです。(現在も普通に販売されています)
粘度が非常に軽いオイルで、不純物が少ない純石油系のオイルになります。
ケーシング内部にゴミが溜まりにくいため、リペアマンにも好んで使用されるオイルの一つです。名前のファスト(速い)の通り軽快なピストンワークで演奏していて気持ちの良い感覚です。
抵抗感はかなり少なく、息抜けが非常に良いです。音が広範囲に拡散していくように飛んでいくため、ホールでのビッグバンド演奏で音を張り上げる際に効果を発揮するかと思います。
息抜けの良さから音にスピード感が出るので、シルキーなどの息がしっかり流れていないと良い音が出ない楽器などにはうってつけのオイルです。
音色はやや明るく、ブルージュースよりは平面的なためクラシックで使用するにはやや物足りなさを感じるかもしれませんが、ブルージュース同様プレーンなオイルなので、楽器やマウスピースのセッティング次第ではどのようなジャンルにも対応できるでしょう。
12. バック
言わずと知れたバックのバルブオイルで、数年前にキャップに誤飲防止用の赤いストッパーが取り付けられました。
粘度は中間よりやや重く、ヤマハのレギュラーと比較してもやや重い粘度を持つ印象です。
オイル自体がバックナイズされた厚みと輝かしい音色を持っており、このオイルを使うとどんな楽器もバックらしい音色に変えることができます。吹奏楽からオーケストラまで幅広く対応可能なオイルです。
抵抗感がしっかりと作られるため息を吹き込んだ時にドスが利きます。迫力のある音で演奏したいタイミングがある曲で真価を発揮するオイルだと感じています。
抵抗が比較的強いオイルなので、楽器に寄りかかりながら演奏する感覚を養う効果が期待できるため、息をある程度楽器に流すことができている初心者にもオススメです。
13. バック・リンズオイル
バック社がトランペット奏者のリン・ニコルソン氏と共同で開発したバルブオイルになります。
リン・ニコルソン氏はメイナード・ファーガソンバンドなどで活躍したプレイヤーで、ジャズやスタジオミュージシャンとして現在も精力的に活動しています。
いわゆるスクリームというスタイルで演奏することが多いニコルソン氏、そんな彼のためのオイルは通常のバックのオイルとは一線を画すものになっています。
粘度は軽く、軽快なピストンワークです。ギラギラと銀色に輝くような音色が特徴的で、常に浅いマウスピースで演奏しているような感覚になります。PDQやブルージュースにこの音は出せません。
まさしくレーザー光線のような音色を手にしたい方にはうってつけのオイルです。こちらは完全にジャズやスタジオミュージシャン向けとなります。
14. トロンバ ファストオイル
T2と同じメーカーから出ているトロンバのファストオイルです。比較的最近発売されたオイルとなります。
T2の粘度が重めだったのに対し、ファストオイルはかなり軽めの粘度となっています。アルキャスよりは少し重い程度でしょうか。
軽いオイルには珍しくクラシカルな音色を持つオイルで、丸く柔らかい音色が特徴的です。抵抗感が軽い楽器は大体ギラギラした明るい音色になる傾向があるので、吹いてみると不思議な感覚です。
T2だと音が詰まり過ぎて、やや重たいなと感じる方には差別化としてこちらのオイルを試してみると、はっきりと違いが感じられます。
特徴的な臭いやゴミの溜まりやすさはT2と同様なので、苦手な方はご注意ください。
15. デニスウィック
ミュートやコルネットマウスピースで有名なデニスウィックのバルブオイルです。
画像を見て頂くと分かりますが、他のオイルが透明なものが多いのに対し、デニスウィックのものはやや濁りがある見た目をしています。
成分の中にPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)が含まれており、これは俗に「テフロン」と呼ばれるものです。テフロンは化学的に安定した成分で、耐熱性に優れていることからフライパンのコーティングなどにも使用されています。
そのため夏の野外での演奏でもオイルが揮発することなく、ピストンの引っ掛かりに悩まされることはありません。
このテフロンのおかげで滑らかなピストンワークを実現しており、他のオイルが「パチパチ、カチカチ」とはまる感触なのに対しデニスウィックは「スルスル」といった感触です。この加工のためオイルが非常に長持ちします。
ダークな音色を持ち、バックのオイルとやや似ていますが、こちらの方がより圧力のかかったような身の詰まった音がします。またバックが拡散するタイプに対し、デニスウィックは指向性があり音が一定の推進直を保ったまま止まらない印象です。
好みやシチュエーションに合わせて使い分けると良いでしょう。
16. ホルトン
ホルトンは1898年に誕生した老舗の金管楽器メーカーです。
かの有名なメイナード・ファーガソンもホルトンのトランペットを使っており、かなりの暴れ馬楽器として有名です。
粘度は中間くらいなので落ち着いた音色を想像するかもしれませんが、吹いてみるとなかなか迫力のある音がします。リンズオイルと通常バックの中間くらいの明るさの音色を持つオイルで、音には張りがあります。
個人的にファーガソンみたいだなと感じましたが、実際にファーガソンがこのオイルを使用していたかは定かではありません。メーカーが同じだと音の方向性が似るのかもしれませんね。
響きが少なくややデッドなので、レコーディングやオンマイクでの演奏に向くオイルでしょう。
ちなみにジャズ向きのマウスピースで吹き込んであげるとレーザービームのような音がするので、興味がある方はぜひ試してみてください。
昔は臭いがかなりあったようですが、近年になり精製技術が上がったためか、多少は軽減されたようです。
17. BSC ハイスピードバルブオイル
ルクセンブルクにて日本人のマイスターが展開するBSC(ブラスサウンドクリエーソン)製のバルブオイルです。
ハイスピードの名に違わぬ軽快なピストンワークを実現できます。息を少し入れただけで音が鳴るだけの反応の良さと、抵抗感の少なさから息抜けが良いため、軽く演奏したい方には大変オススメのオイルです。
明るすぎず暗すぎず、バランスの取れた音色なので楽器やマウスピースのセッティングで大きく変わるバルブオイルの一つでしょう。
18. ウルトラピュア
1990年にバルブオイルメーカーとして誕生したウルトラピュアのバルブオイルです。
メーカーサイトを見たところ化学合成で精製されたオイルのようで、比較的粘度が低いサラサラしたオイルです。
不純物を極力減らすように改良されており、スムーズなピストンワークを実現するために気泡が発生しないようになっています。
個人的にはPDQによく似た粘度を持つバルブオイルだと感じています。そしてPDQは石油系、ウルトラピュアは化学系(シリコン系)なので、それぞれの違いを体感しやすいのではないでしょうか。
石油系は揮発しやすいですが音色が明るくなりやすく、広範囲に拡散するような音になります。
シリコン系は揮発しにくく、音色がある程度落ち着いてまとまりやすく、塊で飛んでいくような音になります。
ウルトラピュアはしっかりした響きと軽やかな音色を持つオイルで、非常にバランスの取れたバルブオイルです。
PDQに並んで人気があり、無臭かつゴミも溜まりにくいので非常に扱いやすいバルブオイルの一つです。
19. ウルトラピュア(ウルトラライト)
ウルトラピュアよりも更に粘度を軽くしたバルブオイルです。ウルトラピュアがヤマハで言うライトなら、こちらはスーパーライトにあたる製品です。
あまり古い楽器だとオイルが流れていってしまいますので、新品の楽器や精度の高い楽器に使うのがオススメです。ヤマハやシルキーとは相性抜群でしょう。
軽い粘度のためピストンワークが非常に軽く、僅かな引っ掛かりもないのでミスできない本番などで効果を発揮してくれます。
ヤマハのスーパーライトに近い明るい音色と軽い吹奏感を持ちますが、スーパーライトほどすっぽ抜けるほどではなく、また音色もややまとまっています。ヤマハのスーパーライトでは抜け過ぎるが近い吹奏感と音色が欲しい方は、こちらのバルブオイルを試してみると発見があるかもしれません。
20. ウルトラピュア(ブラックラベル)
ウルトラピュアの中で最も粘度が高いバルブオイルとして製作され、日本では比較的最近発売された製品です。
とは言うもののそこまで極端に粘度が高いわけではなく、ヤマハのレギュラーやバックより少し粘度が高い程度のバルブオイルになっています。
新品の楽器だと少しピストンを重く感じるかもしれませんが、少し使い込んだ楽器であれば程よくケーシングのクリアランスを埋めてくれるでしょう。
粘度が高いオイルの特徴同様、やや強い抵抗感を持っているので使用する場合には息をしっかりと流してあげる必要があります。音色もほどよく身の詰まったものになるので、好みは分かれるかもしれませんがハマる人にはハマるタイプのバルブオイルです。
21. ノマド
ギター・ドラム等の楽器ケア用品メーカー、MUSIC NOMADが販売している金管楽器用のバルブオイルです。
石油フリーで製作されている、化学合成系のバルブオイルです。
指で触ってみた時点でかなり粘り気があるため、③のブラックラベルよりも粘度が高いのは間違いないでしょう。
トランペットに使う場合には古い楽器でないとクリアランスを埋め過ぎてしまうためピストンの動きを阻害してしまう可能性があります。低音楽器への使用をオススメします。
今回使用した楽器は比較的新しいためかなりの抵抗感があり、音色は丸めでやや張りのあるものになりました。個人的には違う楽器でまた試してみたいと思えるバルブオイルです。
22. アリシン
NASAとの共同開発で生まれたと謳われているアリシン社のバルブオイルです。
アリシン社は元々は車のエンジンオイル等を開発している会社で、その延長で管楽器用のバルブオイルを開発したようです。
数滴の注油で問題ないと謳われているように、非常に高い粘度を持つバルブオイルで、今までの紹介してきたバルブオイルでも最大級です。こちらもノマド同様、指で触って分かるレベルです。
ノマドよりは響きの多い音になりますが、基本的には質量で押していくタイプの音色です。抵抗感はアリシンの方がやや軽く感じられ、トランペットであっても扱いやすいバルブオイルでしょう。
他のバルブオイルと混ざるとバルブの動きを阻害するので、使用する際には必ず楽器を綺麗にしてからにしましょう。
23. アイルリッヒ
マウスピース製作や楽器修理、調整も行っている日本のマイスター、アイルリッヒが出しているバルブオイルです。
こちらは山野楽器ウインドクルーが主に扱っている製品となります。
粘度は軽く、よく抜ける吹奏感ですが凝縮された厚みのある音で、例えるならばPDQからエッジを取って丸さを加えたような不思議な音色です。張りはあるが丸い、と表現するのが正しいでしょうか。吹奏感と出てくる音のギャップに、初めて吹いた時少し頭が混乱しました。
個人的にはPDQがポップス寄りの音色であるならば、こちらはよく似た音色ながらややクラシックに寄ったものだと感じました。吹奏楽などで演奏される方は一度試してみる価値のあるバルブオイルです。
24. FATCAT(高粘度)
猫の顔がドンと印刷されたロゴが特徴的な、ファットキャットのバルブオイルです。
青色のバルブオイルであるこちらは非常に高粘度のバルブオイルで、これまで使用してきた中で最も粘度が高いです。実際に触ってみた感触も、液体というよりはジェルのようで、ピストンに注油した後に指で伸ばさないといけないほどでした。
トランペットよりはチューバ・ユーフォニアムなど大型の楽器かつ、ピストンが摩耗してクリアランスが広がった楽器向けとなっています。
今回私の比較的新品に近いトランペットに使用してみましたが、かなり強い抵抗感と詰まった音になり、やはり楽器との相性が悪かったのでしょう、ピストンワークも良いものではありませんでした。
25. FATCAT(通常)
ファットキャットのバルブオイルです。
ピンク色のオイルが特徴的で、こちらも比較的粘度が高めのバルブオイルになります。
高粘度タイプと同様、どちらかと言えばチューバやユーフォニアムなどの大型楽器向けですが、トランペットに使用しても問題ないと感じました。
化学成分を一切配合せず、高純度の精製油のみで製造されたオイルとメーカー紹介文にあるように、石油系の軽めのピストンワークと高めの倍音を含みつつ、やはり粘度が高いオイルということもありしっかりとした抵抗感と、芯の厚い音色でした。
こちらも新品の楽器よりは、それなりに使い古された楽器の方が適合するバルブオイルだと感じました。
26. JMルブリカント(ライト、No1)
JMルブリカントは、1866年創業と古い歴史を持つ金管楽器用バルブ専門メーカー「J.Meinlschmidt(J.マインルシュミット)社」の製品です。
JM社は最近注目を浴びている『MAWバルブ』や『OPEN FLOWバルブ』なども開発している老舗ながら先鋭的なメーカーでもあります。
こちらのJMルブリカントオイルはノンシリコンを採用したオイルで、バルブの摩耗やサビを防ぐ効果を高めています。
また生産時にCo2排出を極限まで減らそうとした試みもされており、ドイツの楽器に対する情熱と環境問題への配慮の高さを窺い知ることができます。
JMルブリカント全体の特徴として、ヤマハやヘットマンなどと比べると、かなりオープンな音色と吹奏感です。
なので吹奏楽などある程度存在感を出していきたい場合や、オープンな音色が好きな方には、JMルブリカントをオススメします。
こちらのライト系のバルブオイルは、軽めの抵抗感で息抜けが良いですが、音色はどちらかと言えばシンフォニック寄りなものになっています。
27. JMルブリカント(ミディアム、No2)
JMルブリカントのミディアムタイプのバルブオイルで、こちらはピストンだけでなくロータリーにも使用することができます。
ライトタイプよりもさらにシンフォニックな音色ですが、比較的オープンな音色になるので合奏でも埋もれることがない印象を受けました。状態やメーカー含め多くの楽器に適合するバルブオイルだと感じました。
やはりヤマハやヘットマンのレギュラータイプのバルブオイルと比べてもオープンで明るめな音色です。
28. JMルブリカント(ヘビー、No3)
JMルブリカントで最も粘度が高いヘビータイプのバルブオイルで、こちらもミディアムと同様にピストンだけでなくロータリーにも使用することができます。
ヘビータイプとありますが、私はそれほど粘度の高さを感じず、ミディアムより少し抵抗が強い程度かな?と言った印象を受けました。ヘビータイプの中ではかなり扱いやすいバルブオイルではないでしょうか。
バルブワークも高粘度タイプにしては反応が良く、ヴィンテージ楽器でジャズやポップスを演奏してみたい方にはクリアランスを埋めつつオープンな音色で演奏ができるので、オススメのバルブオイルです。
29. アライアンス
コルネットのマウスピースで有名なアライアンス社が販売しているバルブオイルです。
世界的コルネット奏者にして心理学者でもあるロジャー・ウェブスター氏が監修しており、100%石油由来のバルブオイルです。
またアレルゲンとなる物質を含まず、医療的にも問題となる物質をなるべく配合しないよう開発されたバルブオイルのようで、心理学者としての側面を持つウェブスター氏の配慮が窺えます。
粘度はやや高めで、非常に芯のある滑らかな丸い音で、トランペットよりもコルネット向けに製作されたバルブオイルなのではないか、という印象を受けました。
音色ほど吹奏感に抵抗はありませんが、コルネット的な丸い息で演奏してあげないと効果が発揮されないバルブオイルです。コルネット奏者の方や丸い音を求めるトランペット奏者にオススメのバルブオイルです。
30. シルキーウルトラファスト
一時期日本ではあまり見かけなかったシルキーのバルブオイルが復活したようです。
ウルトラファストと名前にあるように、バルブワークはかなり軽く、テンポの速いパッセージでもしっかりと対応してくれると感じました。
吹奏感はPDQやブルージュースなど軽めのバルブオイルに近いですが、クラシック寄りの厚い音色で一瞬頭が混乱しそうになりましたが、慣れるとかなり扱いやすいバルブオイルです。
最近発売されたシルキーのHDシリーズなどのしっかりした楽器や、シンフォニック的な音色を求めつつ軽めの吹奏感が欲しければシルキーのウルトラファストがオススメです。
31. Monster Original
monsterシリーズの中ではプレーンなタイプのバルブオイルです。
トランペットを含む全ての金管楽器に使用できるバルブオイルとのことなので、ピストンバルブを用いる楽器であれば大体使えそうですね。
monsterのバルブオイル全体に言えることですが、音色は明るさと太さがバランス良く共存しています。抵抗感はしっかりとしているので、吹き応えのあるタイプのバルブオイルです。
Originalはその中でも中間の粘度に位置するので、新品からヴィンテージまで幅広い楽器に使っていくことができると思います。吹き込むと圧がかかったような音になるので、ドスを利かせやすいと感じました。
32. Monster faster
Originalより抵抗は少なく息抜けもしやすいですが、これもしっかりとした抵抗感があるオイルです。
Originalよりも粘度が軽く、当然バルブワークが軽いので新品に近い楽器に使用すると効果が発揮されます。
今まで吹いてきの他のファスト・ライト系オイルに比べて、滑らかさのある上品なタイプの音色になります。代わりにギラつくような音色にはあまり近付かない印象があったので、吹奏楽やクラシックに持ち込むと意外に効果がありそうです。
ハイノート音域の抜け感は後述するDoc’s Juiceよりも個人的には良かったと感じました。
33. Monster smoother
monsterのバルブオイルの中では最も粘度があるバルブオイルです。
こちらは言うまでもなく使い込まれてピストンとケーシングにクリアランスが生まれてきたヴィンテージの楽器にオススメです。
ヘビー系のバルブオイルはかなりの抵抗感と凝縮された(時に凝縮され過ぎて詰まった音になることも……)音が特徴ですが、smootherに関してはOriginalに近い音色と吹奏感かつ凝縮され厚みのある音になるので、演奏でも扱いやすいヘビー系オイルだと感じました。
息を一気に流すと反射圧がしっかり来るので、Originalよりも更にドスの利いた迫力のある音になります。
34. Monster Doc’s Juice
fasterよりも更に抵抗感が少なく、monsterシリーズでは一番粘度が軽いバルブオイルです。
トランペット奏者のドク・セバリンセン氏が開発に携わり、本人も使用しているバルブオイルとのことで、実際に使用してみるとドクっぽい音がするなあと感じました。
fasterに比べるとエッジが利いた音になるので、こちらは完全にポップスやビッグバンドなどで使用することで真価が発揮されるバルブオイルでしょう。
宣伝文句の通りピストンワークが最も軽いので、超絶技巧の演奏の手助けになってくれるバルブオイルです。
35. Monster Slide Oil
バルブオイルではないですが、スライドオイルについても今回は試してみました。
こちらのスライドオイルはトランペットの1番管、3番管に使用し、演奏中のスライドによる音程調整を容易にしつつ気密も維持する目的ののです。
トランペットは解放時(ピストンを押さない状態)と1番、3番使用時に抵抗感のギャップが生まれやすいため、これの解消のためにスライドオイルは使用されることが主です。
今回は普段私がスライドに使用しているPDQの代わりにmonsterのスライドオイルを使用し、違いを比較しました。
1,3番管の気密が上がるため、PDQを塗っていた時に比べると明るさは鳴りを潜め、芯のあるタイプの音になります。
スライドオイルはmonsterに限らず、ケーシングに入ってきてしまった際にバルブオイルと混ざってしまいゴミなどが溜まりやすくなる可能性があるので、使用する際にはそれなりの頻度でピストンとケーシングの掃除をしてあげた方が良いでしょう。
まとめ
今回はバルブオイルについて、各メーカーの商品のレビューと実際の演奏を比較で載せさせてもらいました。
私は実際に吹いている側なのではっきりと違いを感じることができますが、映像と音声だけではなかなか違いが分からなかったり、違いが分かっても感じ方が私と違うという方もいらっしゃるかと思います。
そもそもバルブオイルでそんなに違いが出るのかについて、「こんなのプラシーボ効果じゃないのか」と懐疑的な意見を持たれる方がいらっしゃっても不思議ではありません。
しかし多くのメーカーがバルブオイルを出している以上、全く同じということは有り得ないのです。
もしバルブオイルに違いがなければ、日本ではヤマハのものだけが流通していればそれで事足りるはずです。ですが実際にはそうではない。
この記事では30以上のバルブオイルを紹介していますが、各製品に使用されている成分や油の配合などが異なれば、音色や吹奏感にも影響があると考えるのが自然な発想ではないでしょうか。
もちろん、バルブオイルが楽器演奏の全てを決定するわけでは決してありませんが、楽器演奏に変化を与える一エッセンスとしては確実に存在していると私は考えています。
もしかしたら今まで他のバルブオイルを試す機会が無かったという方がいらっしゃるかもしれません。
この記事を見て「もしかしたら違いがあるのかも……」と少しでも感じられたら、今まで使っていたものからいきなり変えるのは勇気がいることだとは思いますが、ぜひ実際に違うものを試してみてください。
今回はここまで、それではまた!
スライドグリスの比較もしています。
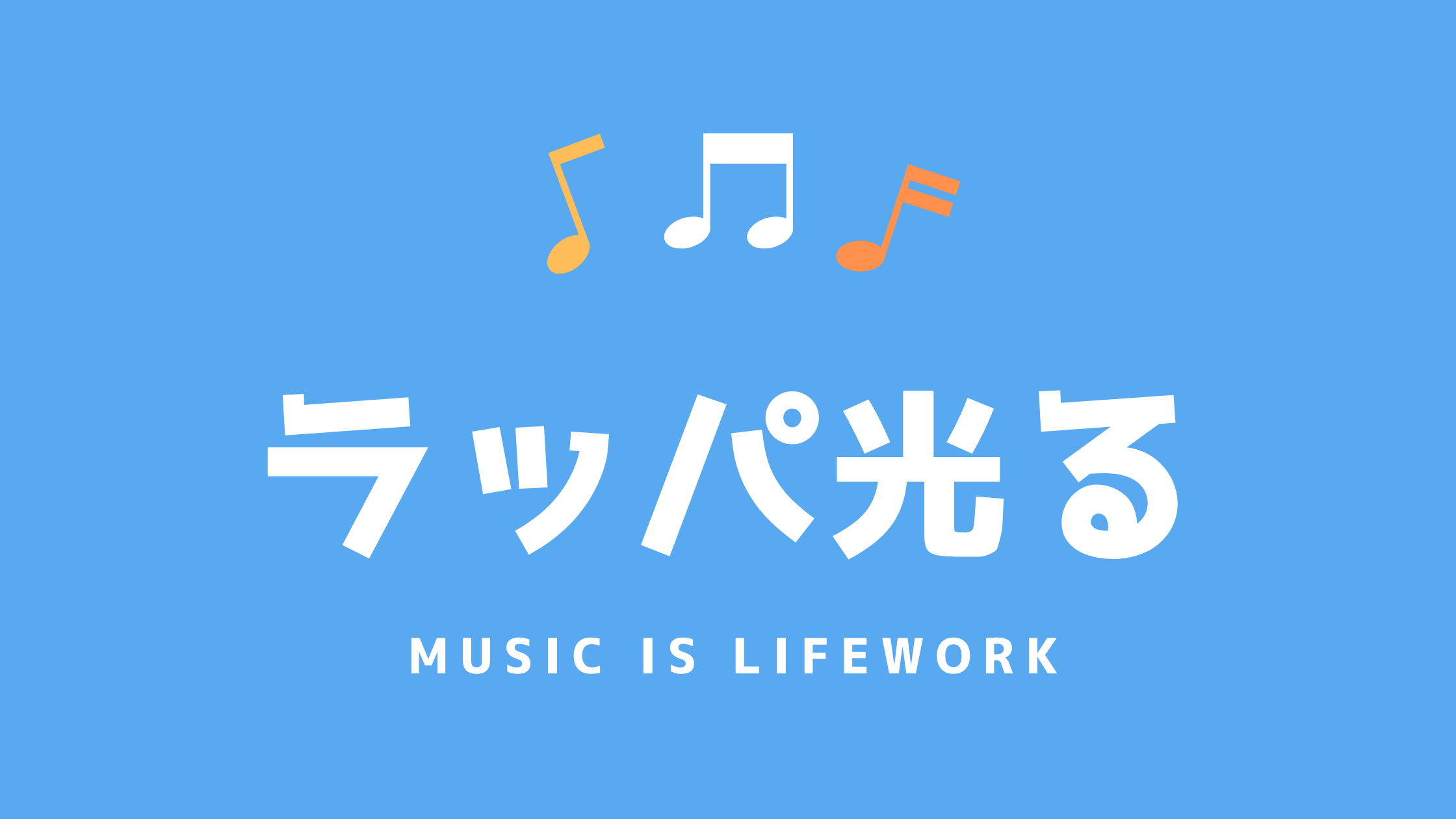




































とても分かりやすく参考になりました!
Great post!